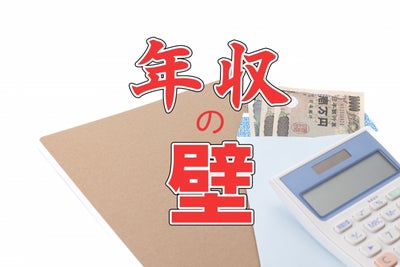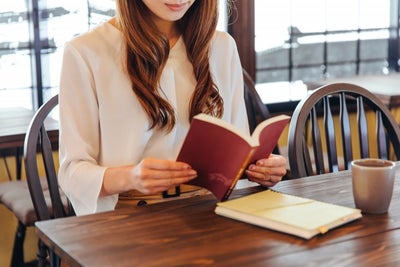日本には、刑務所からの仮出所者や保護観察中の少年に対し、住居や就職先の世話などを通して社会復帰を支援する「保護司」という独自の制度があります。この制度が、国連加盟国・地域に広がる見通しとなり、5月19日にウィーンで開かれる「国連犯罪防止刑事司法委員会」で基本的な指針となる「準則」として採択される方向です。日本の司法制度に詳しい、毎日新聞出版社長の山本修司さんが5月16日放送のRKBラジオ『立川生志 金サイト』に出演し、この話題について解説しました。
世界が注目する日本の保護司制度
保護司というのは、刑務所から仮出所した人や保護観察中の少年らと面接して、住む所や就職先の確保を手助けする人で、非常勤の国家公務員です。といっても、交通費などの経費くらいしか出ない原則無給のボランティアです。
全国に4万6000人ほどいるのですが、平均年齢が65歳と高齢化が進んでいるうえ、昨年5月には滋賀県大津市で保護司が世話をしていた相手から殺害される事件も起きたことで辞める人も出て、保護司の確保には苦労しているというのが実態です。これはあとで触れます。
保護司の活動は、有村架純さんと森田剛さんの共演で映画化もされた漫画『前科者』でも描かれ、人と人との繋がりの中で社会復帰を支える重要な役割が広く知られるようになりました。山本さんは、アメリカ映画「ショーシャンクの空に」における出所者の支援は民間の非営利団体によるものだろうと指摘し、日本の保護司のような制度は海外にはほとんど存在しないと言います。それが今回、「HOGOSHI」として世界に輸出されることになったのです。
保護司制度は、5月19日にウィーンで開かれる「国連犯罪防止刑事司法委員会」で「準則」と呼ばれる、基本的な指針として採択される方向です。これによって、加盟国や地域が立法や政策立案をする際に、この保護司の制度を一つのルールとして参照することになるわけですから、世界に保護司制度が広がると言っていいと思います。
再犯防止への期待
この背景には、各国とも一度罪を犯した人が再び罪を犯す率、再犯率といいますが、これが高いことが挙げられます。
法務省が毎年出している犯罪白書によりますと、刑法犯で検挙された人のうち、初めて罪を犯した人、初犯者は2006年に23万5000人だったのが23年には9万7000人と6割近く減っている一方で、再犯者は14万9000人から8万6000人と4割減にとどまっていて、23年の再犯率は47%と高止まりが続いています。
また、再犯した人のうち7割が無職で、22年に刑務所を出た人のうち出所時に居住先がなかった人の再入率、また刑務所に入ってしまった人は21.8%と全体の再入率の13%を大きく上回っています。つまり、住むところや仕事がない人の再犯率が高いということで、逆に言えば住居や仕事があれば再犯率が減る可能性が高いということです。数字の出し方が違うので一概には比べられないのですが、おおむねこれは諸外国でも同じ状況です。
4年前の2021年3月に京都で開催された「国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)」では、再犯防止が主要テーマの一つとして議論され、各国の再犯率の高さと対策について意見交換が行われました。そこで、日本の官民連携によるきめ細やかな支援、特に保護司制度が高く評価され、今回の国連の場での準則作成につながったのです。
地域社会全体で支える仕組み
先ほど「官民が連携して」といいましたが、これは保護司だけでなく民生委員だとか町内会などといった地域でさまざまな活動をしている人たちも加わっているということを表しておりまして、古くて新しい、また日本らしいコミュニティとして、いい意味でよってたかって犯罪者の更生、社会復帰を手伝っているということで、学校と家庭、地域で子供を育てていくという昭和の日本的な子育てと根っこが同じといっていいと思います。日本が世界に誇るべき制度といえます。
高齢化と担い手不足という課題
しかし、保護司の高齢化や、昨年滋賀県で起きた痛ましい事件の影響などから、保護司のなり手が減少しているという深刻な現状も存在します。このため、新たに保護司に就任できる年齢の上限である現行の66歳を撤廃するとか、インターンシップを通じた公募制の試行、安全な面会場所を確保するなどの改革案も出ているのですが、これだけでは保護司の減少に歯止めがかかるとはいえません。
報酬制の導入も議論されたのですが「自発的な善意を象徴するもので報酬制はなじまない」として見送られています。いずれにしても保護司の人員確保は簡単ではなく、保護司制度を世界標準にできたとしても本家本元が苦しむ状況はそう簡単に変わりそうもないことが、悩みの種となっています。
日本の強みを世界へ
今回の保護司制度の国際的な展開は、日本が持つ優れた制度が世界に認められる一つの事例と言えるでしょう。経済発展を続けるベトナムにおける複式簿記や税法整備への日本の貢献も、その一例です。
日本が国連の準則を通じて再犯防止に向けたリーダーシップを発揮することは、今後、様々な分野で日本の良さを世界に広げていくための先駆けとなることが期待されます。
この記事はいかがでしたか?
リアクションで支援しよう
この記事を書いたひと

山本修司
1962年大分県別府市出身。86年に毎日新聞入社。東京本社社会部長・西部本社編集局長を経て、19年にはオリンピック・パラリンピック室長に就任。22年から西部本社代表、24年から毎日新聞出版・代表取締役社長。